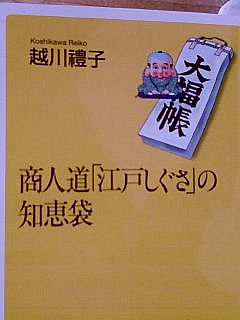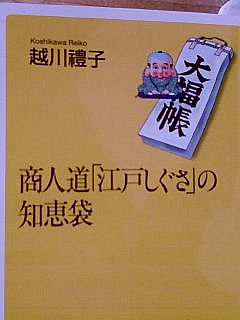
職場はアクトタワーの上階。
毎日必ずエレベーターに乗ります。
朝は特に満員になりますが、すぐに降りるわけではないのに、
乗り口付近で仁王立ちしたまま、動かない方を時々みかけます。
入り口付近に立ってしまったら、降りる人がある度に一旦表へ出て
人の流れをよくし、済んだら戻る。
お互いに狭い空間を共有しているのだから、気配りができれば自然と
譲る行動となる。
江戸の道は、みんなが行き交う天下の往来、
子どもたちが話に夢中になって後ろから来る人に気付かないでいれば、
「背中にも目をつけて歩け」と大人は叱ったそうです。
また、急に立ち止まるのも事故のもと。
電車やエレベーターなど限られた空間で、大きなカバンやリュックを
肩にかけて、人にぶつけても知らんぷりの人が多いのも気になります。
共有空間では自分の占有スペースはなるべく小さく。
荷物は、下ろして前に抱く。
人は前に出っ張っているから、前に抱けばじゃまになりません。
江戸っ子たちは、周囲への気くばりをできない人を「井蛙っぺい」(せいあっぺい)
と言いました。
つまり、井戸の中の蛙は世間知らずで、なんでも、自分がいちばんと思いがち。
人への謙譲の気持ちがなくては、世間は渡れないよ、と戒めたとのこと。
エレベーターで、我先に乗り降りするのも避けたいものです。
参考 越川禮子著「商人道『江戸しぐさ』の知恵袋」
講談社+α新書

 日記/一般| 中央区 (旧中区)|
日記/一般| 中央区 (旧中区)|