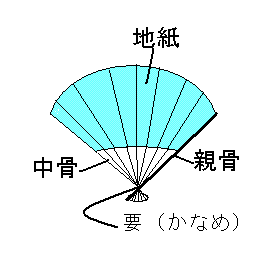
暑くなってくると、本当に役に立つ扇子。
儀礼や儀式のため、踊りに使うため、といろんな役割がありますが、
やっぱり風を送るための扇子の役割が、一番身近です。
扇子のこと、調べてみました。
涼をとるための扇を「夏扇(なつせん)」といいます。
一般に男持ちは七寸三分(約22センチ)、女持ちは六寸五分(約20センチ)
で、扇面は主に紙で作られます。
骨は、竹で出来ていて、閉じたときに外側に来る骨は、「親骨」といい、
扇子を形成している骨は「中骨」といいます。
骨の数は、「桁数」といって、素材や目的に応じて、桁数は変わります。
骨を止めているところは一箇所、「要(かなめ)」といいます。
扇子の要は、金属やプラスチック、鯨ひげなどで骨を束ねています。
この部位が壊れると扇子としての用を為さなくなるため、
「肝心要」の語源となりました。
地紙の貼られた扇面は、絵が施されているもの、渋紙で無地のものなどが
あります。布が貼られているのは、逆輸入の扇です。
扇は、閉じた状態から、骨を右手親指でずらすように押すことで開きます。
逆に無理に開くと壊れてしまいます。
片手ですっと開くと、様子がいいのですが、慣れるまでなかなかそうは
いきません。扇子をお求めになったら、人前で開ける前に是非練習を
してください。
扇ぐ時は、パタパタとせわしなく扇ぐのではなく、
ゆったりと扇ぐのがよし、とされています。
暑くて扇を使うので、ぱたぱたと動かしてしまうのが人情ですが、
使っていただければわかりますが、実際は、ゆっくりと扇いだほうが
風がより起きるようです。
女性は、着物を着た場合、帯に挿して懐剣の代わりとします。
正式な場所へ着物でお出かけの際は、扇を挿して、正装となります。
帯に挿す扇は、抜いて扇ぐためのものではないので、小さめでよく、
塗りで家紋が入っていればなおのこと結構なものです。
挿すときには、要の側から差し込みます。
わたしは、天から挿すのだと勘違いしていて、呉服屋さんで教えて
いただきました。
よく考えれば、天から帯へ挿せば、扇も傷みますよね。
扇子は、茶道のお道具のひとつにもなっています。
茶扇もお茶席で開くことは無いそうですが、扇面には絵が描かれている
とのこと。扇面の絵にも季節感を持たせるのでしょうか。
扇は、その形から、「末広(すえひろ)」とも呼ばれ、縁起がいいとされ、
おめでたい席での贈り物にも用いられます。
ぶん屋では、さまざまな誂えをお受けしておりますが、
塗りの扇子へ家紋を入れる誂えもございます。
女持ち家紋扇の誂えの記事はこちらをクリックしてください。
家紋は蒔絵職人が手描きでいれてくれます。
出来上がりは毎回、ほぉ、とため息の出る美しさです。

 日記/一般| 中央区 (旧中区)|
日記/一般| 中央区 (旧中区)|